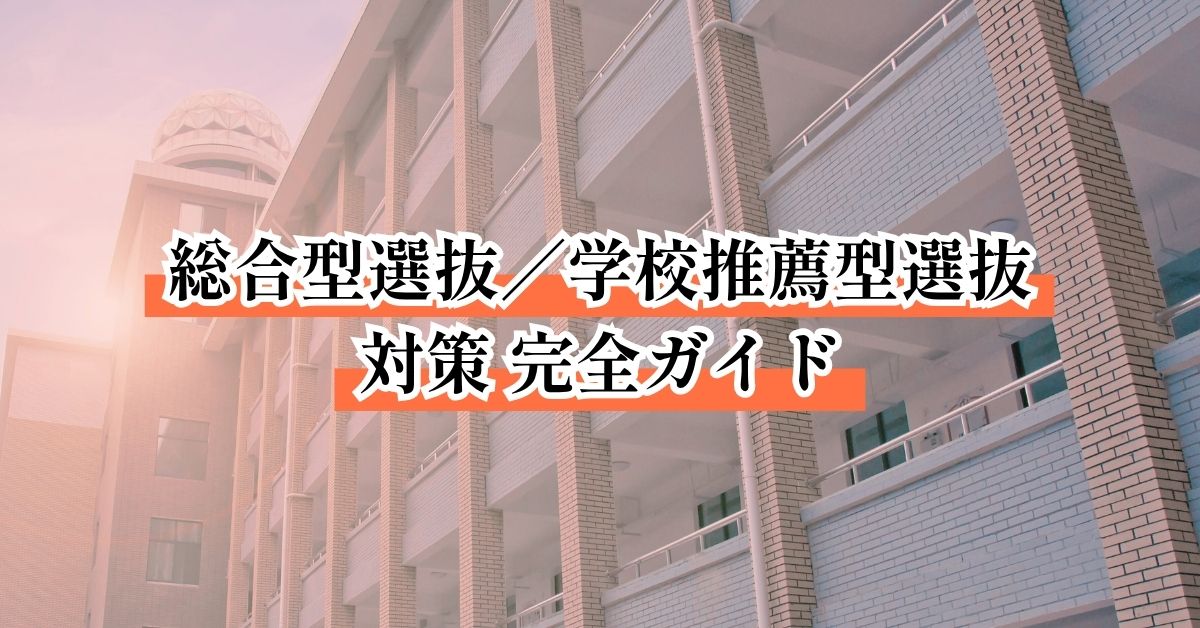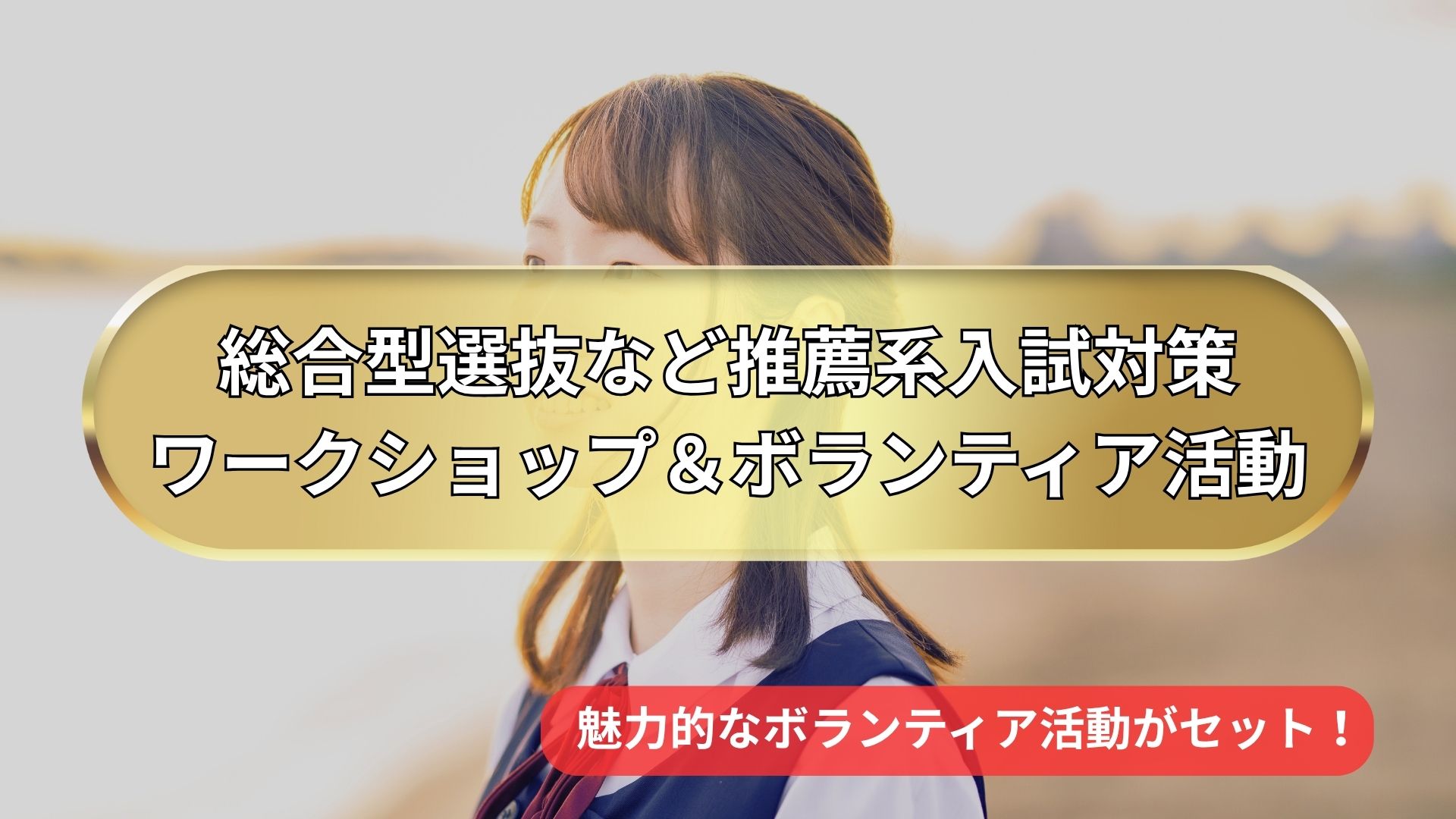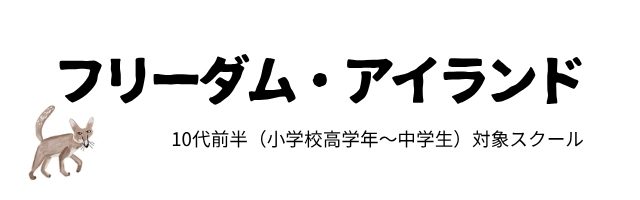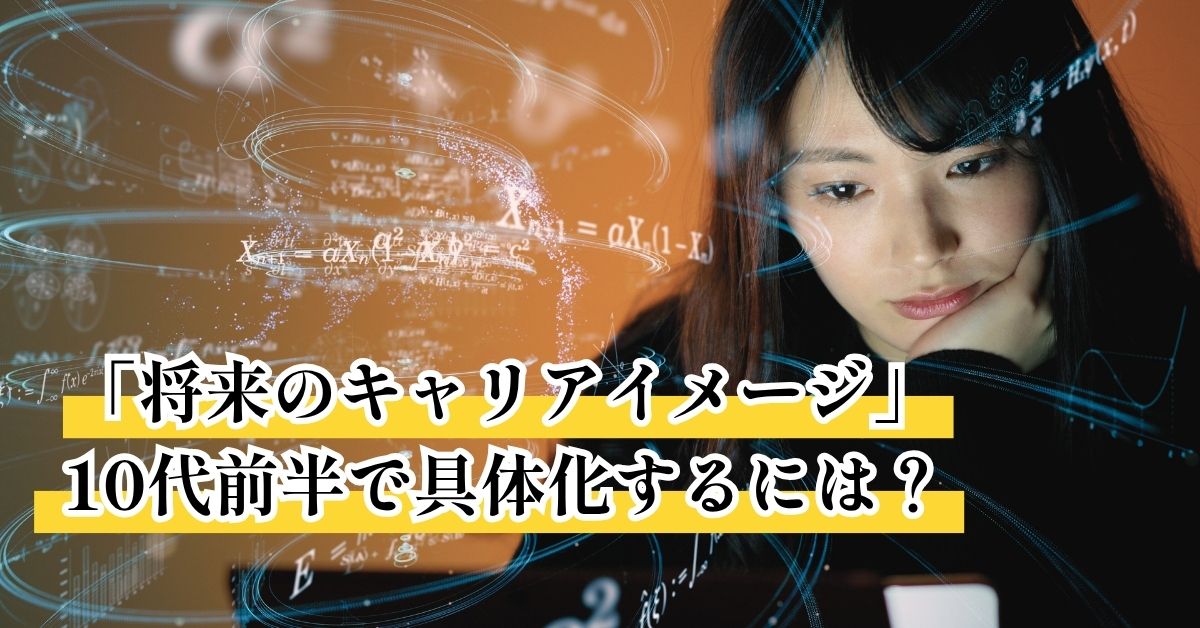
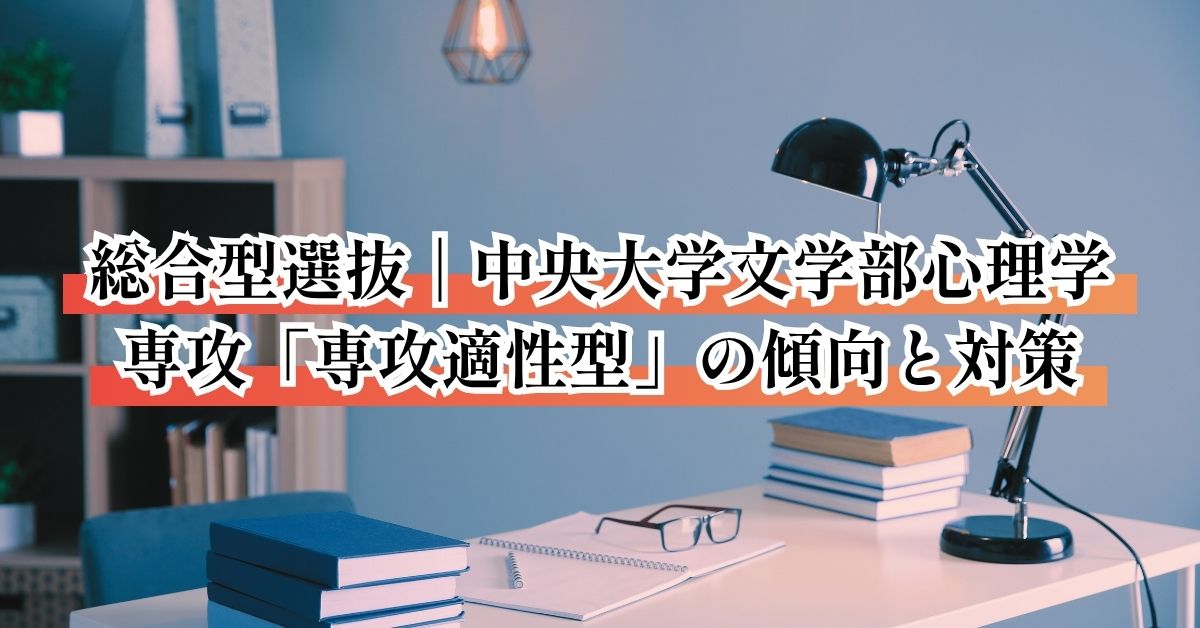
中央大学 文学部 心理学専攻 専攻適性型(総合型選抜)を、出願要件やアドミッション・ポリシーから分析し、合格のための戦略を解説します。
心理学への興味・関心だけでなく、
- 深く考察しようとする姿勢を評価
- 実際に行動を起こしている受験生を求めている
という方向性が明確です。
そのため、評定平均や、志望理由書対策もさることながら、いかに心理学に関連したボランティア経験等を積み、体験から学び、その内容を論理的に説明できるかが勝負になります。
中央大学文学部心理学専攻「専攻適性型」で求められる人物像や資質
中央大学文学部心理学専攻「専攻適性型」の出願要件
心理学に強い関心を持ち、心理学に関する多くの読書経験やボランティア等の経験を持つ者。
https://www.chuo-u.ac.jp/common_d/connect/admission/2026/special/11_1_new0709.pdf
心理学に関する「知識」と「行動」が出願要件とされています。
“心理学に興味がある” という段階ではなく、実際に行動を起こしている受験生を求めている、という方向性が明確です。
中学生や高校1年生の早い段階から、計画的に行動をしてきた受験生が有利です。
アドミッション・ポリシー分析
求める人物像1:人間や社会への幅広い関心と探究心
中央大学文学部のアドミッション・ポリシーでは、
「人間の思考や行動、人間関係や社会構造について深く探究する意欲」
を持つ人を求めています。
単に心理学に学術的興味がある、というだけでは不十分である、という事実がわかります。
たとえば、児童心理学や、関連する不登校の問題に関心があるのであれば、子どもの発達や集団行動そのものに興味を持ち、それを深く考察しようとする姿勢こそ評価されます。
求める人物像2:主体的に学ぶ態度と協働性
心理学に関する知見や関心だけでなく、
「人間と社会に関心を持ち、自ら主体的に学ぼうとする態度と意欲」
を備えた人材を求めている、と明記されています。
面接試験では、特にこの「主体性・協働性」が重視されます。
後述するように、グループディスカッション形式の面接が課され、選抜されます。
自分から積極的に学びに向かい、他者と協力できる経験を示せるかどうかが、合否を分けるポイントになります。
求める人物像3:論理的思考力と表現力
書類審査や小論文では、心理学に関する知識や読書量だけでなく、自分の考えを論理的にまとめ、表現する力が評価されます。
たとえば、何か課題解決のために行動したという実績を志望理由書や小論文に盛り込むとき、解決できたという結果だけでなく、何が原因で、どういう解決方法がベストなのか論理的に考え、自覚的に行動できたかどうかを評価するということです。
その分析や判断を支える、知識の範囲や絶対量も重視されると見るべきでしょう。
心理学専攻の選考適性型では、ボランティア経験が求められますが、単なる課外活動とするのではなく、心理学への関心と主体性をアピールするための切り札として位置付けることが戦略上重要です。
そのために、ボランティアに取り組む目的意識を明確にし、得られた経験を出願書類や面接で最大限活かす方針を立てましょう。
中央大学文学部で求められる学力水準
公式に評定平均の足切り基準等は明示されておらず、次のように提示されています。
高等学校段階までの学習において、国語、外国語、歴史、数学等の内容を幅広くかつ十分に理解している。
“幅広く、十分に” をどう解釈するかですが、素直に読めば、定期テストで8割前後は取れる水準が安全でしょう。
中央大学文学部の一般選抜(テスト入試)の合格水準を考え合わせても、評定平均4.0前後が最低限必要で、それ以上は高ければ高いほど有利に働く、と考えておきましょう。
また評定平均は全科目の平均値ですが、アドミッション・ポリシーでは「国語、外国語、歴史、数学等」とあえて明示されていますので、この4教科の評定は重視されるとみなすことができます。
評定平均が3.5程度だったとしても、国語・外国語・歴史・数学の評定だけを見れば平均4.5ある、という場合は、勝算ありと判断できます。
なお、あくまでも評定平均=高校の調査書は、選考に使われる資料の一つという位置づけです。評定平均が良かったとしても、それだけで合格を勝ち取れるわけではありませんので、注意が必要です。
総合型選抜でのアピールの仕方(基本)

「行動の伴った志望理由」が圧倒的に強い
総合型選抜では、将来のキャリアイメージから出発して、それを実現する手段として志望大学・学部学科を選び、
“私がいかに大学にふさわしいか”
をアピールするのが基本です。
しかしながら現実には、多くの受験生が「入学できたらやりたいこと」を語るにとどまります。
たとえば中央大学文学部心理学専攻で言えば、
「心理学を学んで人の心を支えたい」
「中央大学で理論と実践を学びたい」
などという受験生が多いかもしれませんが、どれも動機として素晴らしくはあるのですが、これらは “願望”の段階にとどまっており、評価は低くなってしまいます。
特に出願要件で、
心理学に強い関心を持ち、心理学に関する多くの読書経験やボランティア等の経験を持つ者。
と明示されるほどですので、口で希望を示すだけでなく、
「私はすでに動き始めています」
という “行動の証拠” を示す必要があります。
自分の興味・関心に基づいて多くの心理学書を読み、ボランティア活動をしながら多くの実感を得て、先を見据えて成長をする経験が必要です。
合格に近づく「逆算型」の発想
総合型選抜では、
10年後の将来の目標やイメージ
↓
そのために今すべきこと
↓
だからこの大学を志望する
という逆算型のストーリー構築が求められます。
✅ 目標はあるけど何もしていない受験生
✅ 目標に向けて既に行動している受験生
面接官・評価者の目に、どちらが本気に映るかと言えば、言うまでもなく後者です。
「私は本気でこの分野に進みたいと思っているし、そのためにもう動き出している」という強力なメッセージを打ち出すために、将来のキャリアイメージを早期(中学生時代や遅くとも高1まで)に固め、積極的に行動しましょう。
心理学を学びたい理由を語れることは当然として、
“既に心理学的関心を持ち、実際に心理学に関わる現場に飛び込んで行動している”
という実績をアピールできるかどうかが、合否の分かれ目になります。
将来のイメージをどのように具体化すればよいかは、次の記事で詳しく解説しています。
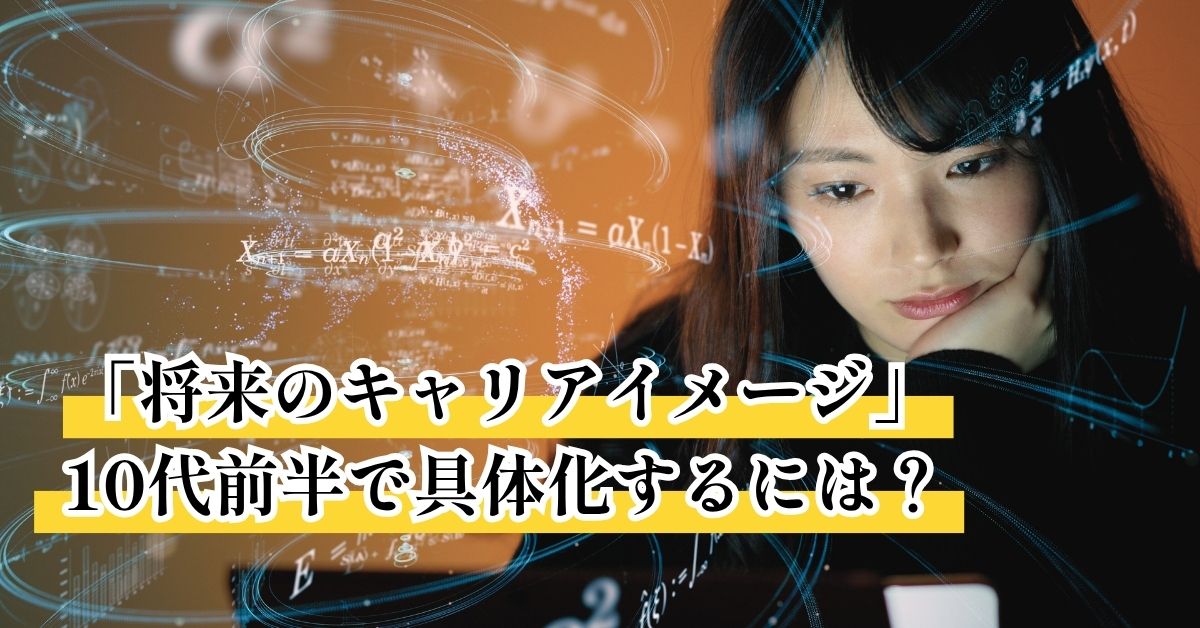
また、総合型選抜の特徴と対策を、もう少し詳しく確認しておきたい方は、次の記事をご覧ください。
選考種類別のボランティア活動の活かし方

中央大学文学部心理学専攻「選考適性型」では、
心理学に強い関心を持ち、心理学に関する多くの読書経験やボランティア等の経験を持つ者。
という出願要件から、読書経験と、ボランティア活動等の経験が合否を分けるポイントになります。
しかしながら、読書経験については、「この本を読んでおけば合格できる」といった特定書籍は特にないと考えるべきで、特別な対策はできません。
(自分の成長に繋げられるかがポイントですので、将来のイメージから逆算して、何が必要かを考え、多くの心理学の知見に触れられるようにしましょう)
そのため、実質的に対策のポイントとなるのは、ボランティア活動ということになります。
出願書類からグループディスカッションまで、様々な選考が行われますが、ボランティア経験をどのように反映させればよいかを解説します。
1. 志望理由書
ボランティア活動の活用例:ボランティアで得た経験を、心理学に対する関心の深化や探究心の芽生えとして位置づけ、中央大学での学びと接続する。
***
志望理由書では「なぜ中央大学文学部心理学専攻を志望するのか」を書きます。
その中に、ボランティア経験で得た学びを盛り込む方向が王道です。
例えば、
「◯◯な人と関わり、△△のような変化を目の当たりにした。この経験から✕✕について更に学問的に探究したいと感じた。中央大学では心理学科に所属しながら社会学部のフィールドワークにも参加できると知り、理論と実践の両面から学べる環境に魅力を感じた」
といった形で、経験→学び→志望動機の流れを論理的に述べます。
オープンキャンパスなど、中央大学での実体験(参加した体験授業など)や、魅力を感じているカリキュラム・システム等はある場合は、「大学で何を学びたいか」を具体性を持って伝えられるよう、積極的に活用します。
2. 活動内容説明資料(任意提出)
ボランティア活動の詳細・期間・目的・役割を具体的に記載し、出願要件の「心理学に関するボランティア経験」に該当する活動であることを明示するために、活用しましょう。
提出は任意ですが、ボランティア経験をアピールする絶好のチャンスです。提出する方向で準備するのを強くおすすめします。
資料には、活動期間・場所・内容の概要に加え、自分の役割や学んだことを簡潔にまとめます。
自身の主観だけでなく、写真や、スタッフ・他ボランティアからのフィードバックコメントなども含め、信憑性と具体性を高めます。
ポイントは、単なる日記的記述ではなく、心理学専攻の出願要件に該当する活動であることを示す書き方をすることです。
「心理学への関心にもとづきこの活動に参加し、◯◯のような心理的サポートを行った」
「(興味のある分野)の観点から、心理学の実践に通じる貴重な経験となった」
など、要件に合致する内容を盛り込みます。
総合型選抜は、試験官の印象に残るかどうかの勝負、という側面もあります。
調査書や経歴書には書ききれない詳細を、この資料で補足することで、書類審査段階から評価者に強い印象を与えることができます。
3. 小論文(3,000字程度/心理学書2冊以上を取り上げて論述)
ボランティア活動の活用例:小論文で扱う書籍の心理学理論を、ボランティア活動の現場で実践して実感を得たり、書籍の内容を補強する(あるいは反証となる)体験をしたりして、小論文の説得力を高める。
***
合格を目指すにあたって最重要と言えます。
小論文で扱う予定の書籍内容から、「これは現場で試せそう(確認できそう)」という知見をピックアップし、ボランティア活動の中で活用・検証するという方向性が王道で、強力なアピールに繋がります。
特に、書籍の主張に対して「現場で実際に違和感や限界を感じた瞬間」を拾い、批判的視点として活かせば、評価につながりやすいでしょう。
逆に、「まさに本に書かれていた通りのことが起きた」という共鳴的体験も、論文の説得力を高める材料になります。
このように「読んで学んだことを現場で試す→効果や課題を実感する」サイクルを回した体験を示せれば、
“既に心理学的関心を持ち、実際に心理学に関わる現場に飛び込んで行動している”
ということが評価される選考基準ですので、大きな武器になります。
自分の言葉で具体例を交えて書けるため、説得力が増す事実も見逃せません。
ボランティア運営団体との連携が必要
書籍で学んだ心理学理論の検証の場としてボランティア活動を活用する場合には、運営団体との連携が欠かせません。
しっかりと主旨を説明し、理解を得た上で行う必要があります。くれぐれも、独断で行ったり、活動の本来の目的に支障が出たり、迷惑をかけることのないよう、注意しましょう。
また運営団体にきちんと説明をするためには、事前にしっかりと活動内容を設計しておく必要があります。「なんとなくボランティア参加をする」では、アピールできる実績にはならない、と理解しておきましょう。
※FREEDOM ISLAND(フリーダム・アイランド)- 高等部ならば、ボランティア活動の場の提供、および大学入試でのアピールを前提としたボランティア活動の目的設定からサポート可能です
二次試験:講義理解力試験(講義後に小論文記述)
講義を聴講後に小論文を作成するという試験内容のため、ボランティア活動を直接的に活かすことは困難です。
ただし、実践経験を積めるため、小論文執筆の際に具体例を経験談として提示できたり、「抽象的な理論を現場にどう落とし込むか」という視点を持って執筆できたり、というメリットは出てくるでしょう。
あくまでも、多くの経験を積んだからこそ、副次的に強みになる可能性がある、というものです。
二次試験:集団面接(ディスカッション形式)
こちらもディスカッションテーマが事前にわからない以上、ボランティア活動を直接的に活かすのは困難です。
しかしながら、集団面接では、他の受験生との差別化がポイントになるため、テーマに応じてボランティア活動での具体的なエピソードを話すことができれば、面接官の興味を引く題材になります。
試験の前に、「ボランティア活動で印象深かった出来事ベスト3」等を整理しておき、それぞれ自分がどう行動し、何を考え、何を学んだかを1~2分で話せるよう練習しておくといいでしょう。
例えば、「ある内気な参加者が初日は発言できなかったが、自分が傾聴に徹しサポートするうちに最終日にみんなの前で意見を言えた」というエピソードがあれば、それを協働性(チームで支え合った経験)や主体性(自分から粘り強く関わった姿勢)のアピールに繋げられます。
また、「問題発生時にどう対応すべきか」というテーマが設定された際には、「想定外のトラブルがあり、咄嗟に優先順位をメンバーと話し合って決め直し、無事収めることができた」等、【冷静な判断力】【協調した問題解決】【子どもの自主性を促した経験】を交えてディスカッションに参加することができます。
このように経験をエピソード化して蓄えておけば、質問に応じて適切な話を引き出せるため、緊張する面接でも落ち着いて自己アピールができます。
ただ「私はこう思います」というだけの受験生に比べて、実践に裏打ちされた説得力がありますから、強力な差別化に繋がります。
【参加者募集】3〜5日間で、志望理由書・面接で胸を張ってアピールできる実績を手に入れる!ワークショップ&ボランティア活動
大学入試の総合型選抜や学校推薦型選抜(指定校推薦、公募制推薦)、そして就職活動で、必ずと言っていいほど問われる、
「協働性」「コミュニケーション力」「課題解決能力」
に関連するボランティア活動実績を手に入れよう。
ボランティア活動の目的設定からサポートし、そのまま志望理由書の作成に活用できるボランティア証明書を発行いたします。