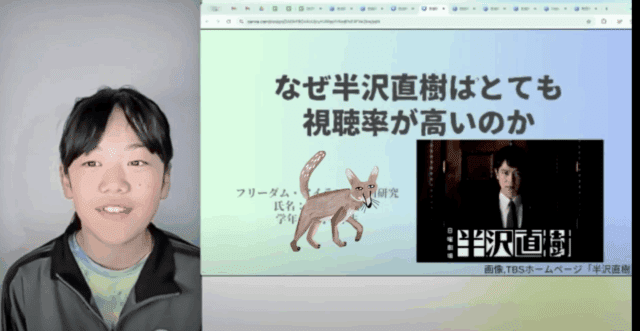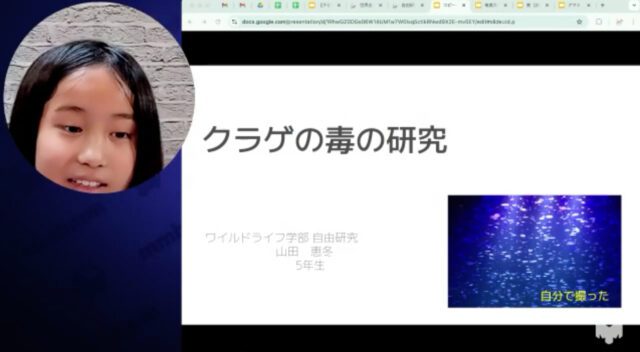自由研究発表会 – 探究プレゼン・ラボ by フリーダム・アイランド
目次
小中学生対象|自由研究の顔をした探究プレゼン・ブートキャンプ!
高校の探究〜ビジネスシーンでも通用する“研究&プレゼンの型”が身につく
夏休みの自由研究と言いつつ、工作をしたり、絵を描いたり、旅行記のようなものを書いたり…… なんだか研究とは違うんだよな、と感じた経験はありませんか?
研究とは、「仮説 → 検証 → 総括(→ 仮説の再構築 → 検証…)」の一連の流れを指します。
型さえ知っていれば、お子さんが自分で興味を持った対象を、なんでも立派な自由研究や探究学習にすることができます。
研究の流れを自然になぞれる魔法の「自由研究フォーマット」を使い、小中学生でも苦労なくコツをつかめます。
また、生成AIによる研究方法のアイデア出しをワークショプでサポートしており、正しいAIの活用の仕方も学べます。
昨今、小学校・中学校でも「調べ学習」や「発表」の機会は増えています。
高校で必修の「総合的な探究の時間」、そして将来のビジネスシーンでも通用する研究の組み立て方や、プレゼン・スライド作成を、この機会に身につけませんか?


楽しく学べる&身につく、3つの理由
「意外とできちゃうね!」という成功体験
大人でも苦手意識があるケースが少なくない、研究発表やプレゼン。フリーダム・アイランドでは、子どもたちに「なるほど、こうやればいいんだ」「思っていたより簡単だね」と感じてもらい、苦手意識が生まれないようにすることを最初の目標としています。一度経験し、コツを掴んでしまえば、自信がついたという報告が多数。
「聴衆を飽きさせない」が最優先
「真面目に発表しなきゃ」というマインドだと、“朝礼の校長先生の眠くなる話” しかできません。しかし、現実のプレゼンで大人が頭を悩ませるのは、いかに興味を持ってもらい「伝える」という目的を達成するか。スライドもトークも、ついクスっと笑ってしまう要素を盛り込むなど、いかに飽きさせないか?を最優先に考えます。
賞金あり(最大13,000円)
親が経験させたいと思っても、「えー、めんどくさい」という反応を示す10代前半は多いでしょう。だからこそあえて、記念品などではなく、受賞者には「自分で自由に使える賞金」を用意。受賞者は、視聴者投票で公平に決まりますので、自信にもなりますし、進学時に課外活動の実績としてアピールすることも可能です。
ただ提出するだけ……だった夏休み課題を「立派な研究」にしよう
自由研究の作り方、評価基準など
研究・レポート作成の基礎をしっかり身につける

昨今、小中学生でもスマートフォンを所持しているケースが多く、宿題をするのにも「ググる(Google検索)」や「チャッピー(ChatGPT)」が当然になりました。
もちろん、学校では使わないように指示するでしょうが、それは建前です。
私たち保護者としては、使われるものと思っておいたほうが良いし、何よりテクノロジーから遠ざけるのは、子どもの学びを考えたときに後ろ向きな考え方です。
さて、ChatGPTに代表される生成AIは便利ですが、調べ物に使ってはいけない、とご存知でしょうか。
なぜなら、生成AIとはその名の通り、オーダーに従ってそれっぽい回答を生成するシステムであって、正解を提示するためのものではないからです。
たとえば「この写真をジブリっぽい絵に変えて」とオーダーすると、ジブリではないけれどジブリっぽい偽物のイラストを出力してきます。
調べ物でも基本的には同じで、ネット上にある情報をかき集めて、それっぽい回答を生成しています。
つまり、前提となるネット上にある情報が間違っていたり、不正確であったりすれば、出力される回答も間違ってしまうわけです。
これを知らずに学校の課題を出力させたり、ビジネスの資料を作らせたりすると、とんでもないミスをしてしまいます。
一方、生成AIが真価を発揮できるのは、アイデア出しです。
様々な可能性を検討するということにかけては、人間を凌駕する場面が増えます。
そのため自由研究発表会では、ChatGPTを使って、研究の方法や手順のアイデアを出し、よく自分で検討したうえで研究の枠組みを決定しています。
これからの時代、避けて通れない「正しいAIの使い方」をも学べるプログラムです。
文責/よりかね隊長
研究=「仮説 → 検証 → 総括(→ 仮説の再構築 → 検証…)」の一連の流れである、と冒頭で説明をしました。
これは具体的にどういうことでしょうか?
たとえば、ただ絵を描いただけでは「うまくできた」「思ったようにいかなかった」等だけで終わってしまいます。
そもそも絵を描くことは研究ではない、と思うかもしれませんが、これも立派な研究にすることが可能です。
「海の質感をうまく表現して描きたい」とテーマを設定してみましょう。すると、質感を表現するためにはどうしたらいいのか?を考え、仮説を立てることができます。
・複数の種類の青を使ってみる
・筆のタッチ、使い方がポイントなのではないか
・青だけでなく白も使ったら波がうまく表現できるのではないか
あとは実際にやってみて検証をして、どうだったか振り返ります。
「いろいろな青を使ってみようと思ったけれど、結局どれを使っていいのか迷ってしまってうまくいかなかった」というふうにです。
そして最後に「我流ではうまくいかなかったから、次はYouTube動画で学んでみよう。うまいと思う海の絵を真似してみるのもいいかもしれない」と、得られた成果を発展させます。
ここまでをまとめたら、立派な「海の描き方」の自分なりの研究レポートと言っていいでしょう。
コツさえ押さえれば、どんなテーマでも立派な “研究” になるんです。
文責/よりかね隊長
受賞作一覧|フリーダムアイランド自由研究発表会
10 Videos

10:12
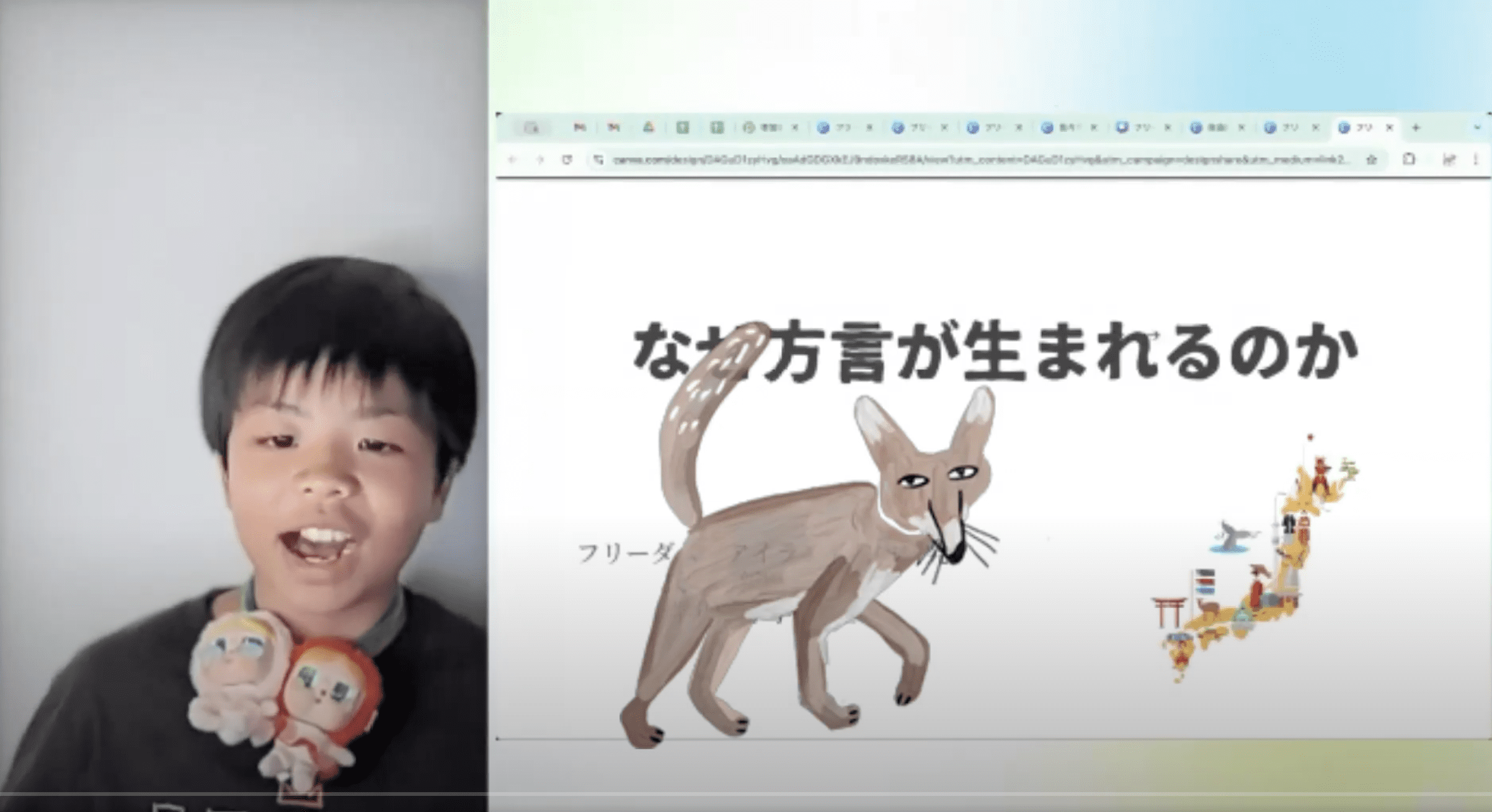
12:38
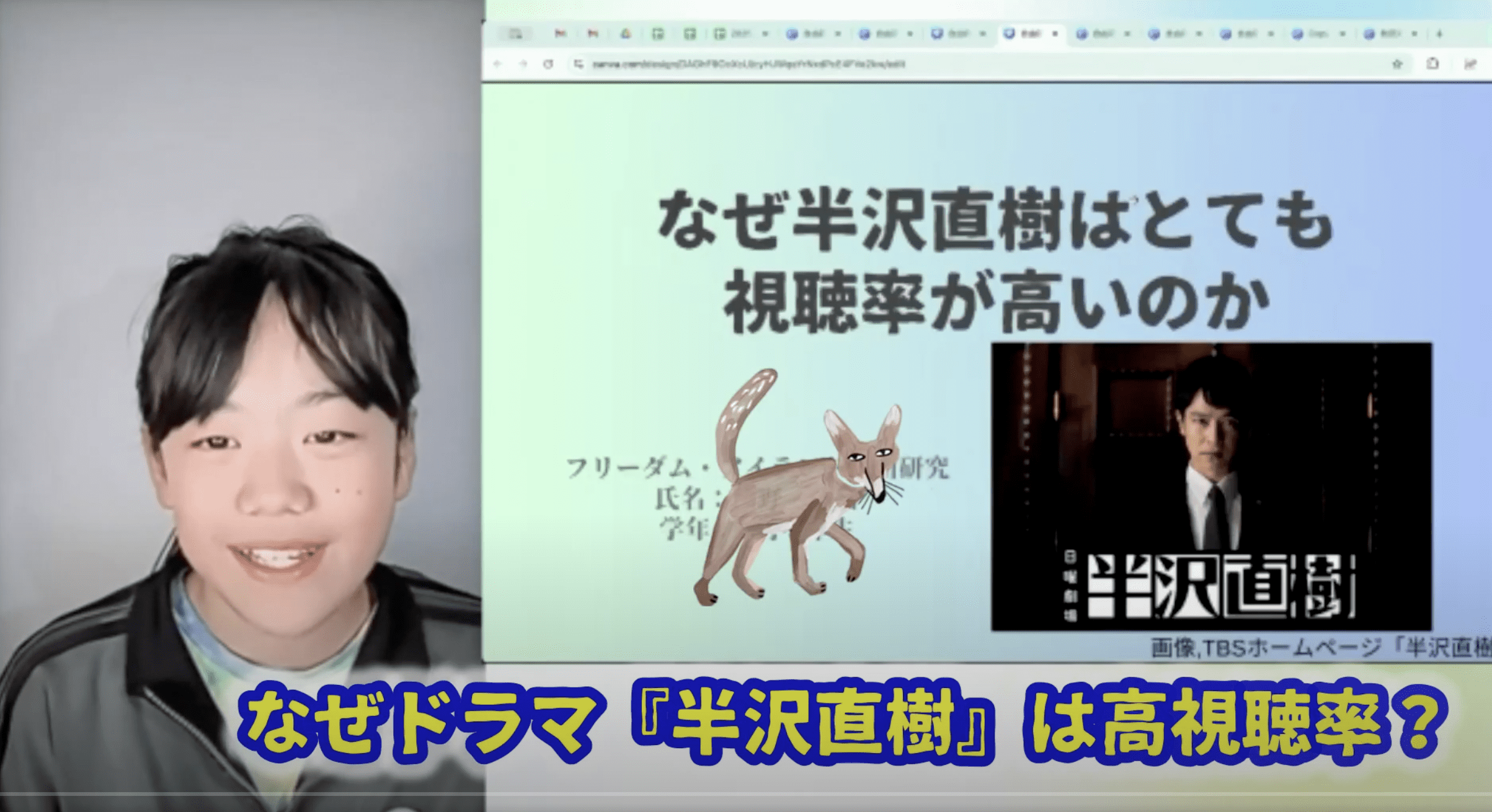
10:19
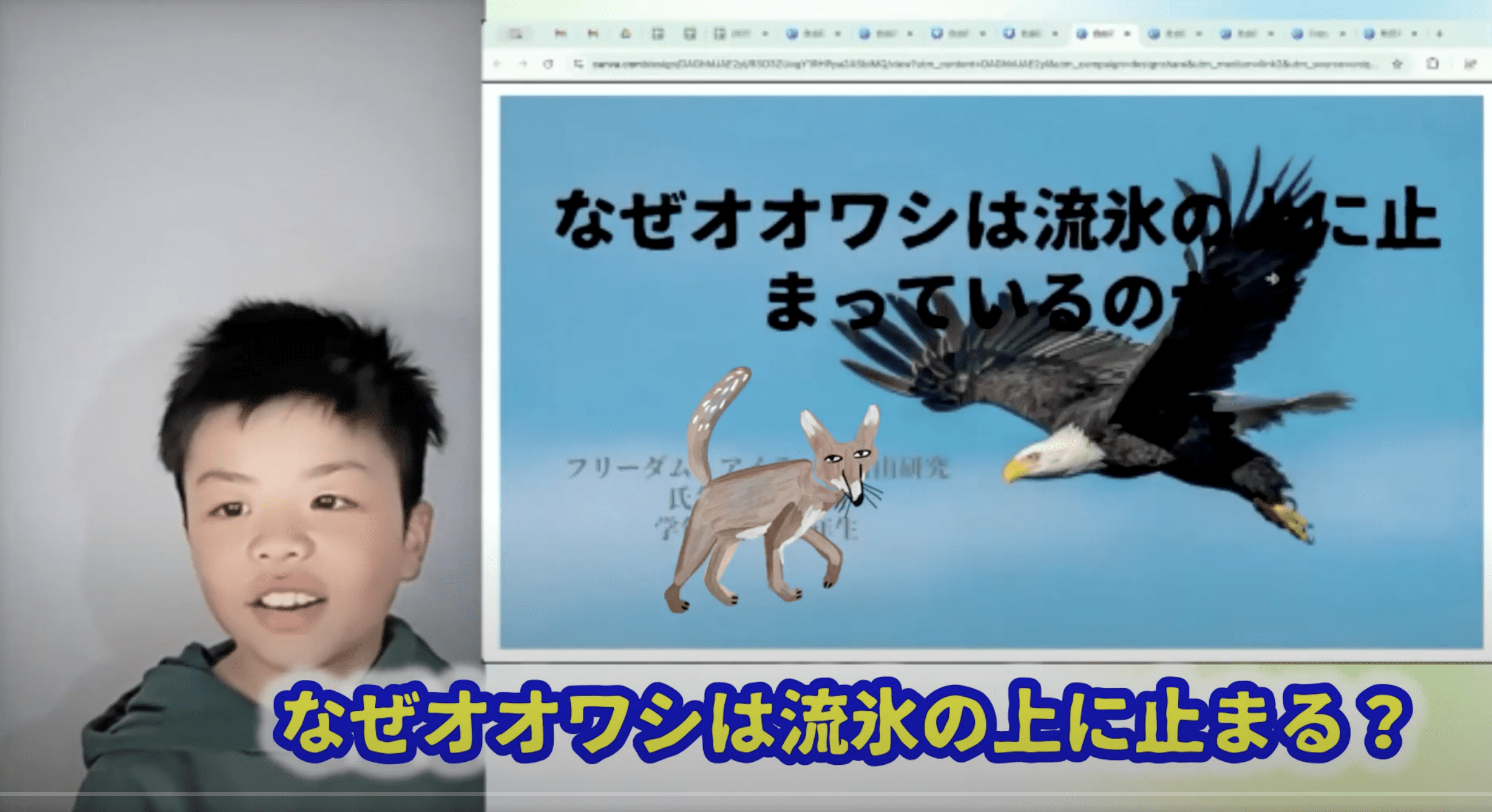
12:18
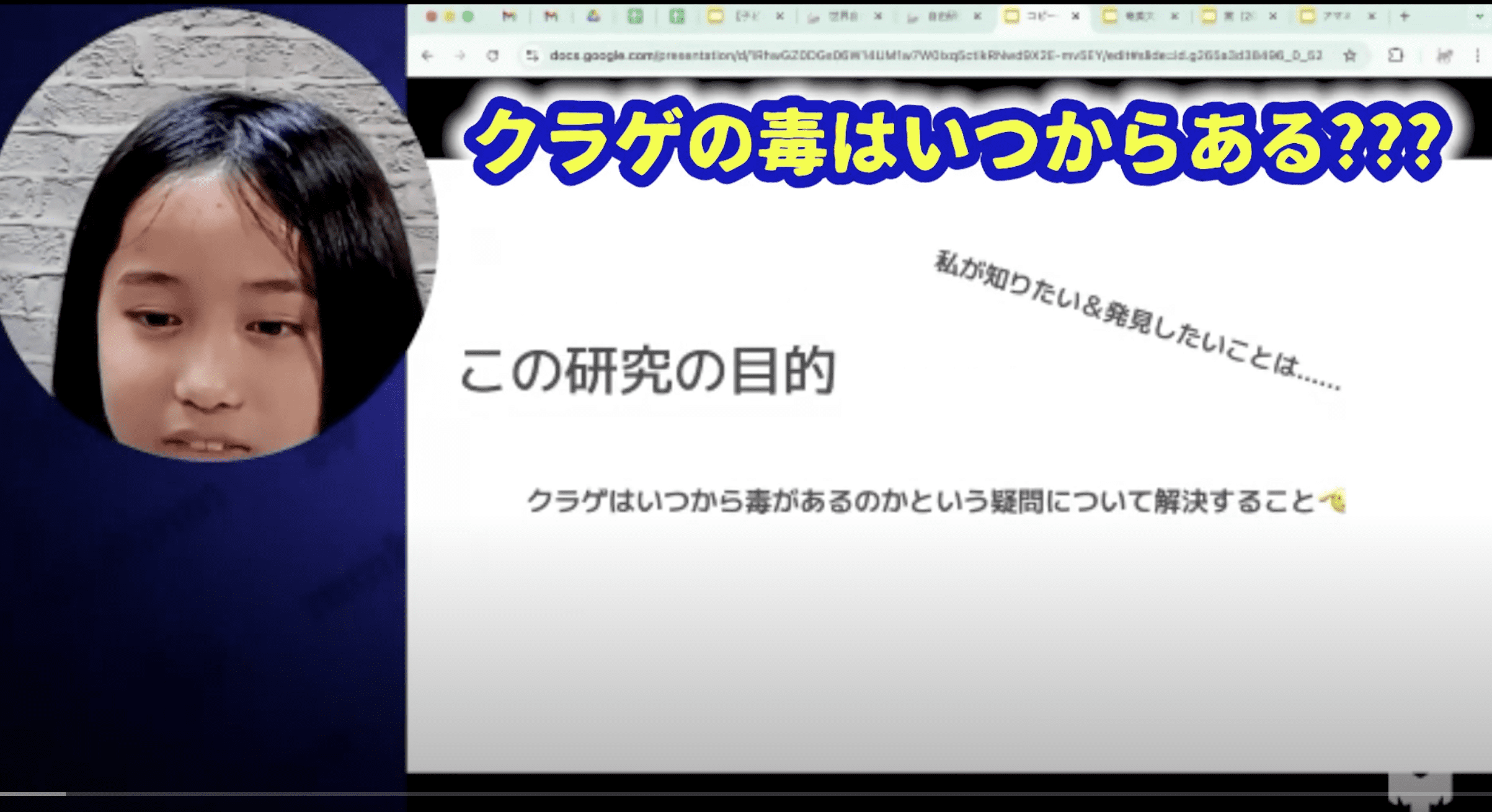
4:00
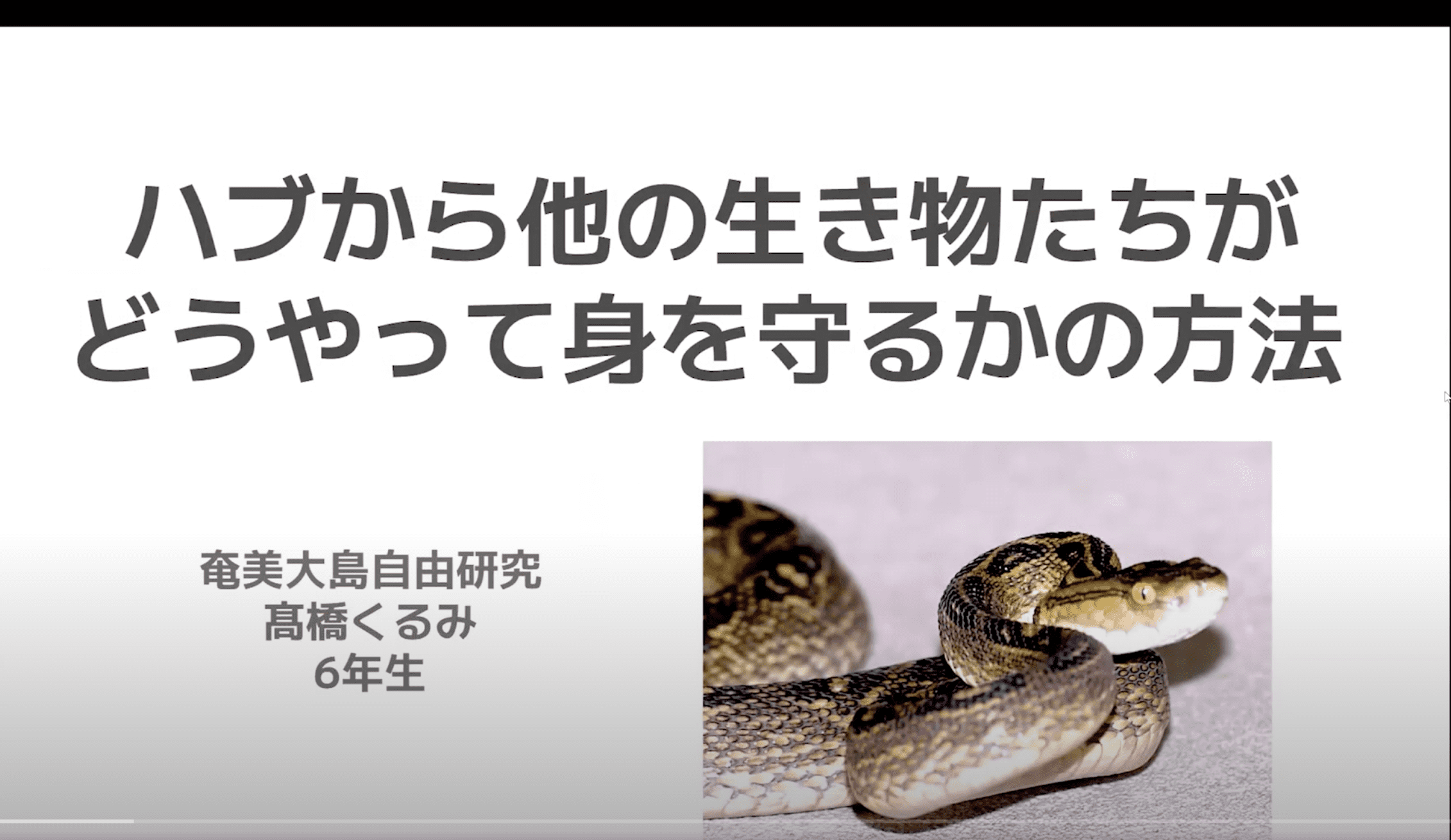
8:17
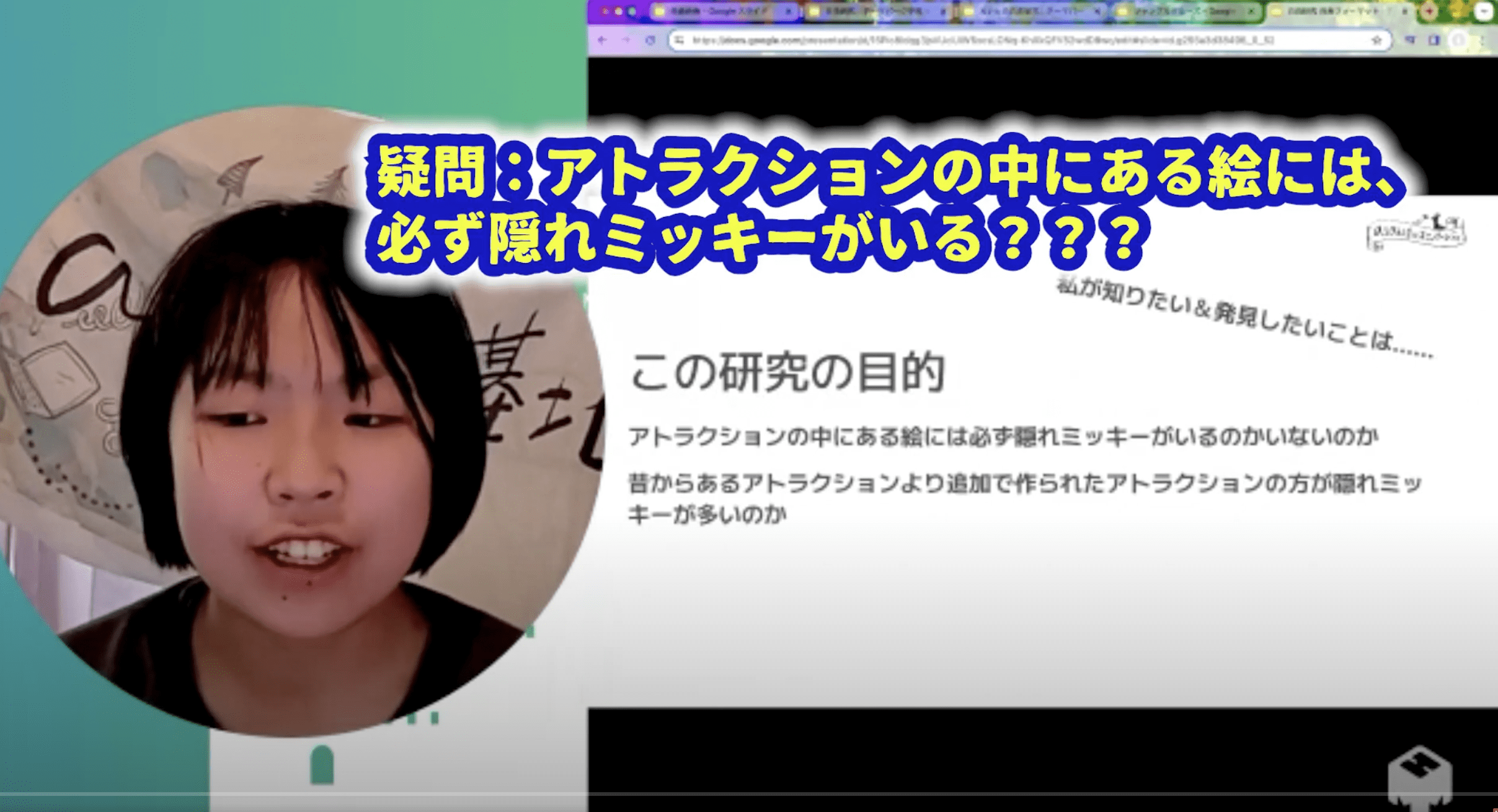
10:14
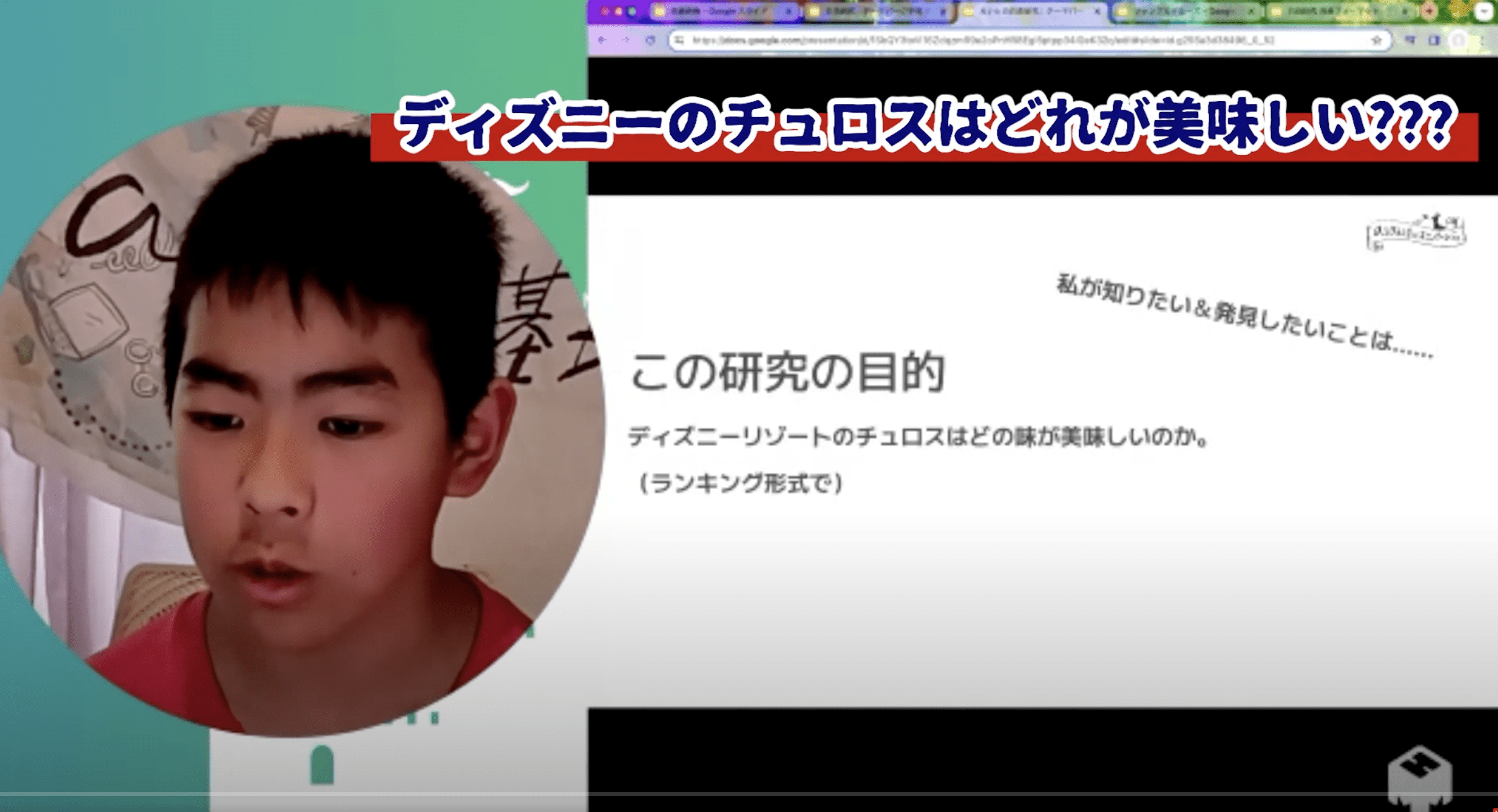
11:02
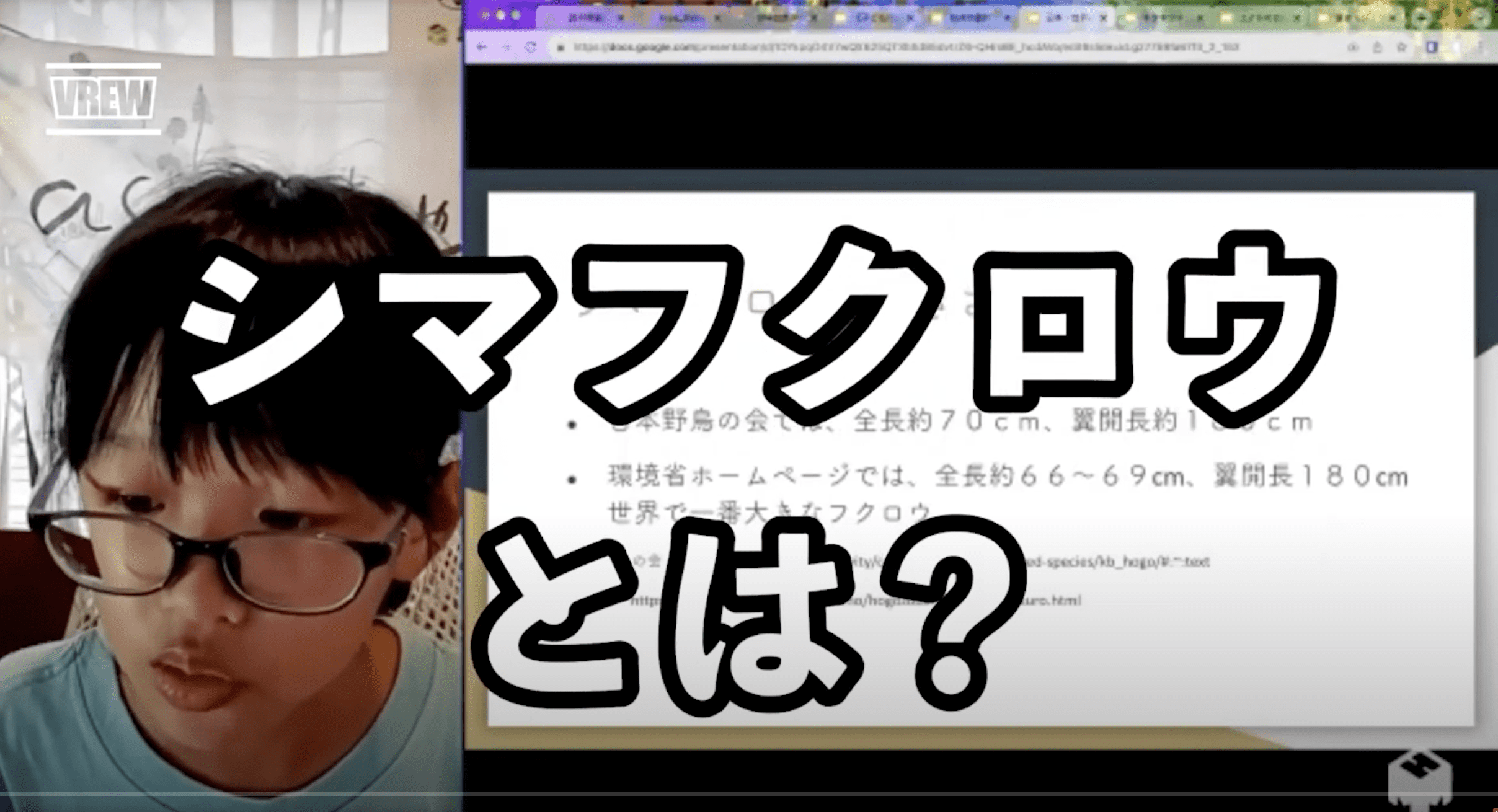
9:51
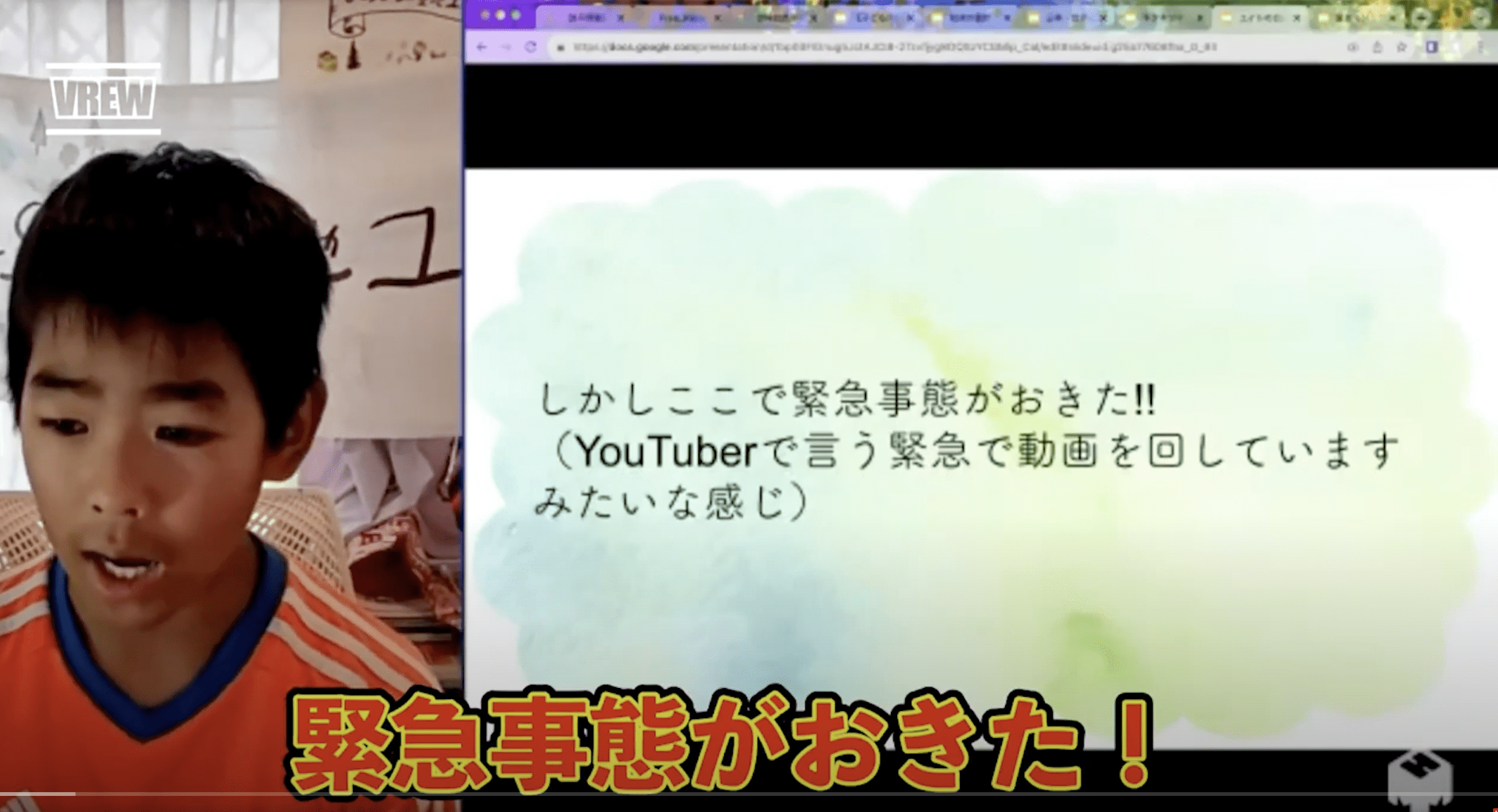
6:27
3つの評価基準
評価基準1:自分らしさを発揮できたか
子どもたちの個性は様々であり、また今の段階でできることとそうでないことがあって当然です。
ですから私たちは、「真面目に発表したか」「ちゃんと喋れたか」などの基準では評価をしません。
発表会では、参加者と視聴者の投票によって受賞者を決定していますが、そこでの基準も、良し悪しではなく「一番好きだった発表」への投票を求めます。
評価基準2:見ていて飽きない発表だったか
プレゼンテーションの最重要課題は「いかに聴衆を飽きさせず、興味を持ってもらえるか」。
大人になってプレゼンをするときに、最も頭を悩ませる要素です。
子どもたちには、自由研究づくりを通じて、「必ず、笑いを盛り込むなど、聴衆を飽きさせない工夫」をするように伝えます。
スライドにギャグを書き込んだり、YouTuberよろしくトークで笑わせようとしたり、笑わせるのが苦手なら写真や図をたくさん盛り込む努力をしたり。
最も笑えた発表に与えられる「エンターテイメント賞」も、投票によって決定しています。
評価基準3:調べた情報は信用できるか
ネット検索をしたり、AIを使ったりすれば、簡単に情報を集められる時代です。
しかし!集めた情報が正しいかどうかは、まったくの別問題。
間違った情報で組み立てられた発表は、ちょっと「研究」とは言えませんよね。
発表会では、AIで集めてきただけだとうまく答えられない、「それ、本当に正しいですか?」「どうしてそう思いますか?」という質問に、うまく答える必要があります。
自由研究発表会のレギュレーション
◇発表資料の作成フォーマット
すべての参加者が「Canva」の自由研究発表フォーマットを使用します。
※埋めていけば研究の流れに沿った自由研究を作成できるフォーマットです
◇発表の持ち時間
10分以内(必ず発表の練習をして、時間をはかって、10分以内に収まるか確認しよう)
※時間超過はNG。短い分にはOKです。4分の発表が大賞を取ったこともあります
◇参加スタイル3パターン
- 会場で、会場のパソコンを使って発表
- 自宅からオンラインで発表
- 事前に発表を動画撮影して参加
◇受賞者の選定
発表者の投票(自分以外に投票)、および視聴者投票で決定。
◇賞の種類と賞品
①大賞
「最も好きだった研究発表」部門で最多得票者に贈られます。
賞品:トロフィー、自分で自由に使える賞金5,000円
②エンターテイメント賞(旧・爆笑で賞)
思わずクスっと笑ってしまった/飽きずに夢中になって聞いてしまった、など「最も面白かった研究発表」部門で、最多得票者に贈られます。
賞品:自分で自由に使える賞金5,000円
③デザイン賞
「スライドづくりが上手かった」部門で最多得票者に贈られます。
賞品:自分で自由に使える賞金3,000円
***
※各賞は重複します。1人の子がすべて受賞する可能性もあります
※その他、全員に賞状があります
参加に必要な機材等
◇PCまたはタブレット
- スマートフォンは非推奨(画面が小さすぎて作業がしにくい/発表がやりにくいため)
- 自由研究作成ワークショップでは、持ち運びができるノートPCまたはタブレットが必要です
- 自由研究発表会にオンライン参加する場合は、カメラ・マイク付きPCであることを確認してください
◇プレゼンテーション作成ツール「Canva(無料)」
- タブレットの場合は、アプリをインストールする必要があります
参加にあたっての注意点
- 自宅の回線でZoomを使用した経験がない場合は、実際にZoomビデオ通話を試して、問題なく通信できることを確認してください
- Zoomで画像が荒かったり、音声が途切れたりしてしまう場合は、せっかくの発表が台無しになってしまう可能性があります。非常にもったいないですので、回線に不安がある場合は事前録画での参加をおすすめします
【事前録画での参加の仕方】
- Zoomのレコーディング機能の使い方を確認する
- 一人でZoom通話をスタートさせ、Canvaをプレゼンテーションモードにし、画面共有
- レコーディングをスタートさせ、発表を開始
- レコーディングを停止すると動画ファイルが作成されるので、内容を確認
- うまく録画ができていれば、動画ファイルを送付
※録画参加の場合、動画ファイルの送付は、発表会の前日18:00締切となります。ご注意ください