
フリーダム・アイランド代表のよりかね隊長です! 長女が、中学3年生の春休みに、大学入試の1次審査が免除される認定証を獲得することができました。
この認定証は、学校の成績やテストの点が基本的に問われず、面接(探究学習等の活動内容に関連する質疑応答)のみで大学受験が可能となるものです。
偏差値にあまりこだわらず、興味を持つ力を武器に進学・キャリア形成を考える場合には、非常に魅力的な事例ではないかと思います。
フリーダム・アイランド「自由研究発表会」でのレポート作成・プレゼンテーション、および受賞の経験が、大きな後押しとなっていますので、具体的に事例を紹介します。
「興味を持つ力」を最大の武器に!学校の成績を問わない大学入試・総合型選抜
近年、大学入試では、テストでの受験(一般選抜)での入学者が5割を切り、学校推薦型選抜(推薦入試)や総合型選抜が存在感を高めています。
具体的な入試の状況や、入試形態・選抜方法については「総合型選抜、学校推薦型選抜|大学入試の特徴と対策の考え方 – fly away」にて詳しく解説していますので、参考にしてください。
推薦入試や総合型選抜の大半は、学校の成績(内申点・評定平均)が問われます。
しかし、特に総合型選抜においては、選抜方法に決まりはなく、大学・学部ごとにバラエティに富んでいます。中には学校の成績をほぼ問われない入試も存在します。
スポーツ推薦をイメージすればわかりやすいですが、スポーツでの実績や将来性を確認できれば、ことさら学校の成績(学業)を問う必要はないわけです。
今回紹介するのは、探究入試の事例です。スポーツの代わりに、高校までの探究学習の成果や、それに類する個人活動・コンテストでの実績等が評価されます。
なおかつアドミッション・ポリシーに合致しているか(その大学ならではの環境を活かして、社会で活躍できるように成長するビジョンがあるか)の勝負になります。
偏差値ではなく、夢中になる力を武器に進学・キャリア形成を考えたい場合に、まさにうってつけと言える入試形態です。
桜美林大学の総合型選抜「探究入試Spiral」ディスカバ!育成型
ワークショップで成果を出せば1次審査(書類審査)免除
長女が中学3年の春休みにチャレンジしたのは、桜美林大学の探究入試Spiralの「ディスカバ!育成型」です。
これは簡単に言うと、大学主催のワークショップに参加し、一定以上の成績をあげられれば、大学入試の1次審査を免除する、というものです。
免除される1次審査は、書類審査で、
- 高等学校の調査書
- 探究学習報告書
- 探究学習・活動の成果物
などです。
学校の調査書の審査が免除されるということは、つまり、基本的に学校の成績(内申、評定平均)が問われないということです。
2次審査は、
- 書類審査
- 出願書類および活動内容をベースとした質疑応答(課題図書の内容理解含む)
となっています。
書類審査(学校の調査書)が含まれていますが、公開されている評価基準を参照すると、学校の成績には一切触れられていません。
よほど酷い成績の場合に足切りされたり、他の評価基準で甲乙つけがたい場合に学校の成績で差がついたりする可能性がないとは言えませんので、学業を捨てて良いというわけではありません。
しかし基本的には、シンプルに「高校までに何をしてきたか」「大学・学部の環境を活かして成長するビジョンがあるか」が問われると見ていいでしょう。
探究入試Spiralは、合格率が高いのも特徴です(ディスカバ!育成型のみではなく、探究学習評価型、コンテスト活用型も含む数字です)。
2024年4月入学入試の探究入試(Spiral)専願の合格率
- リベラルアーツ学群 5/6(83%)
- ビジネスマネジメント学群 14/18(78%)
- 健康福祉学群 3/3(100%)
- 芸術文化学群 4/5(80%)
- 航空・マネジメント学群 3/4(75%)
- 教育探究科学群 8/8(100%)
ワークショップ参加で問われるのはグループワーク、発表、事後レポート提出等
「ディスカバ!」とは、桜美林大学が主催する、高校生向けのキャリア支援ワークショップです。
ビジネスマネジメント学群、リベラルアーツ学群など、大学の学部に関連した内容で、様々なワークショップが開催されています。
そのうち、一部のワークショップで、今回紹介している1次審査が免除になる認定証を受けることができます。
長女がチャレンジしたのは、「ディズニー探究キャンプ(3days来場)」です。
「ヒット商品をマーケティングしよう」というテーマの元で、グループワークを行い、最終日にはテーマパーク論の第一人者である山口有次教授・桜美林大学副学長の前で、発表(スライドを見せながらプレゼンテーション)をします。
さらに参加後にレポートを提出します。
回答項目
- 今回の探究成果についてまとめて説明してください。
- 今回の経験を通して感じた、自分の成長や課題について説明してください。
- 今回の学びを自身の探究や大学での学びにどう活かすか、見通しを説明してください。
- 今回の学びを踏まえて、大学入試までの準備期間に、今後の探究や大学での学びのために何をしようと思いますか?計画を教えて下さい。
レポートの回答項目は、まさに総合型選抜らしい内容で、活動からの学びと、将来のビジョン、今後の具体的な活動計画を問うものです。
すでに総合型選抜での入試準備を進めていて、将来のキャリアイメージが具体的になっており、実績を積み重ねてきているのであれば、それほど難易度は高くありません。
逆に、将来のキャリアイメージがまだなにもない、という場合には、認定証を得るハードルは上がります。
※総合型選抜の入試形態の特徴や、対策の考え方は、「総合型選抜、学校推薦型選抜|大学入試の特徴と対策の考え方 – fly away」にて詳しく解説しています
フリーダム・アイランド「自由研究発表会」の経験はどのように活きた? 3つの視点
1. 中学生ながらメンバーの緊張を和らげようと立ち回れるほどの余裕
「ディズニー探究キャンプ(3days来場)」最終日の長女の発表の様子を、動画で見せてもらいました。
発表の内容そのものは、取り立てて優れているとか、斬新だとかいうわけではありません。基本をおさえた、平均的な水準といったところでしょうか。
しかし、非常に堂々と、臆せずにプレゼンできていたのが印象的です。
聞けば、グループメンバーが緊張しすぎていたのを見て、緊張を和らげようと立ち回っていたとのこと。
この余裕がどこから来るのかと言えば、間違いなく、フリーダム・アイランドの「自由研究発表会」での発表の経験でしょう。
長女は、フリーダム・アイランド「自由研究発表会」で2回発表しており、そのうち1回は大賞を受賞しています。
中高生であれば、大半は、人前で発表するというだけで、過度の緊張に陥ります(もしかしたら、大学生や大人であっても同じかもしれません)。
これは多くの場合、経験不足や、「やり方がよくわからない」という苦手意識が原因です。
しかしきちんと方法論を学び、実際に経験してみると、「ああ、こういう感じでいいんだ」「やってみると意外とできちゃうな」に変わります。
フリーダム・アイランド「自由研究発表会」では、きちんと喋れたかどうかや、ちゃんとできたかどうかでは評価をしません。まず苦手意識を払拭するということが、非常に大事だからです。
中には、すごくあがり性で、「人前で発表しなさい」みたいな場では、声が出なくなるほど緊張するタイプという子が、余裕たっぷりに発表したというケースもあります。
2. ワークショップ参加をためらわず、どんどんチャレンジできる
臆せずにプレゼンできたというのは成長ですが、そもそもそれ以前に、苦手意識があったら、ワークショップへの参加そのものを拒否した可能性が高かっただろう、と思います。
つまり、子どもの興味・関心が広がっていたとしても、グループワークや発表に苦手意識があったら、機会を活かすことができないわけです。
今回、参加する前から、認定証の獲得に明確な勝算があったわけではありません。気軽にチャレンジしてみたらいいんじゃない、というスタンスでした。
気軽にチャレンジできるということそのものが、10代にとっては大きな武器なのです。
そしてこうした気軽なチャレンジが、また経験値になり、その次のチャレンジを容易にします。
逆に言えば、チャレンジに踏み切れないというだけで、どんどん差をつけられてしまいます。
3. 発表歴、受賞歴が事後レポートでの大きなアピールに
ワークショップ参加後に提出するレポートの回答4項目のうち、前半2項目は、参加したワークショップそのものでの成長を問うものです。
しかし後半2項目は、将来のキャリアイメージが固まっているかどうかと、すでに計画的に行動しているかどうかで、アピールの強度がまったく変わってきます。
③今回の学びを自身の探究や大学での学びにどう活かすか、見通しを説明してください。
④今回の学びを踏まえて、大学入試までの準備期間に、今後の探究や大学での学びのために何をしようと思いますか?計画を教えて下さい。
長女の場合は、フリーダム・アイランドの「自由研究発表会」に参加し、なおかつ将来のキャリアイメージも固められていたおかげで、次のようなアピールポイントがありました。
- 「人の心を動かすイベントとは?」をテーマに、中学2年から研究を始めている
- 2024年春には自由研究発表会で大賞を受賞できた
- 様々なイベントやエンターテイメントを経験し、探究を深めていくため、高校も課外活動に専念できる環境を選んでいる
- 今回のワークショップで、自身の研究テーマに関連して、●●という気づきがあった
- これを活かして、高校在学中には●●という計画がある
- 大学に入学できたら、環境を活かして、●●を実現したい
「これから始めます」と「もうすでに行動を始めていて、計画もあります」では、説得力がまるで違います。
しかし、一般的な中学、高校に通っているだけでは、なかなかここまで具体的にアピールすることは難しいでしょう。
もちろん、「自由研究発表会」だけで、キャリアイメージを固めることはできないのですが、発表して評価された経験や、賞を受賞した経験は、将来を具体的にイメージする大きなきっかけとなりえます。
長女の場合も「自由研究発表会」で大賞を受賞して、大きな心境の変化があったようです。
興味を持つ力を活かした進学・キャリア形成の流れ
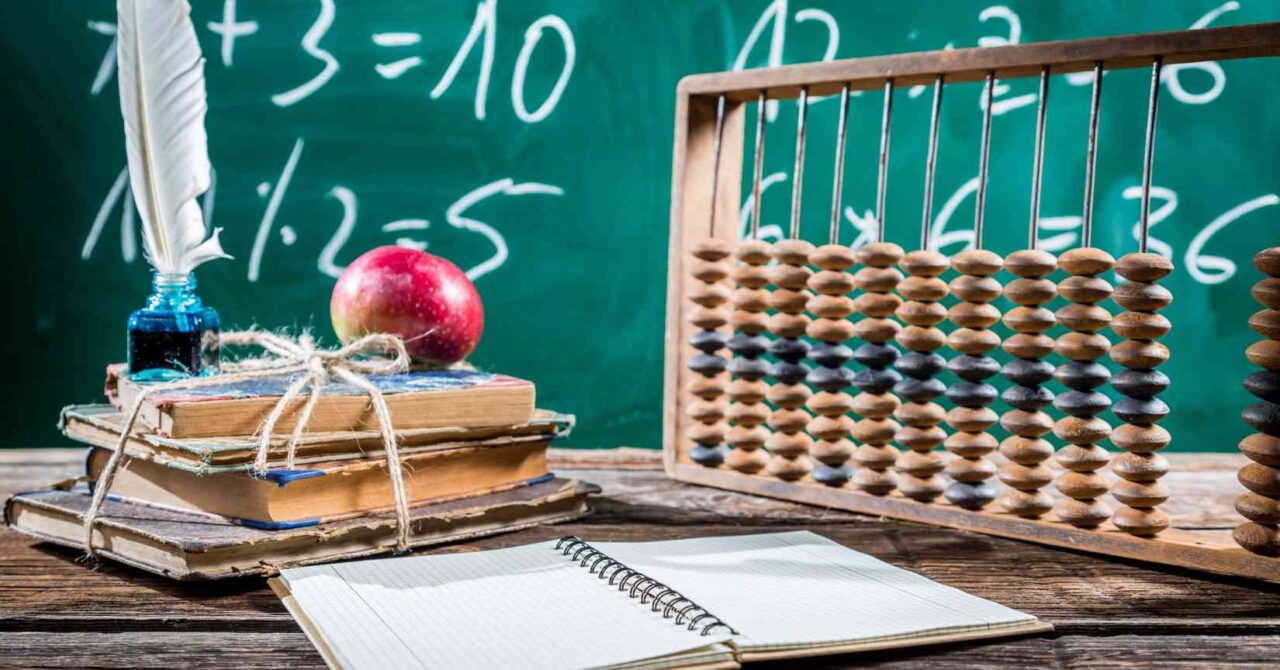
最後に、興味を持つ力を活かした進学・キャリア形成を行うために、長女にどのようなアプローチをしてきたかを紹介します。
最も重要なのは、子どもが自分の足で立って、自分で歩き始めること。
そのために親は何ができるか?
10代前半以降は、親の干渉を嫌うようになるのが発達段階として一般的ですので、過干渉は現実的ではありません。
なにより、自分で必要性を実感して取り組むようでなければ、成長スピードが上がりません。
1. 興味・関心から始まる
自分の人生を自分の足で歩いていけるように、と考えるなら、すべては「興味を持つ力」から始まります。
長女の場合も、世界が広がるようにと、幼少期から「やりたい」という意欲を大切にしつつ、玉石混交の多彩な経験を重視してきました。
今回の長女の事例では、ディズニー研究のワークショップに参加しましたが、2010年代は私がディズニー関係の仕事をしており、なおかつ年間パスポートもありましたので、長女は100回前後は東京ディズニーリゾートに行っているはずです。
ディズニーのパレードやショーはもちろん、映画や劇団四季など、エンターテインメントには積極的に触れさせてきました。

一方で、キャンプや釣り、スキー&スノーボードなどアウトドアにも年間50日はくだらないくらい連れ出しています。春に女子高生になりましたが、未だにスノーボードや釣りは誘うと「行きたい」とついてきます。
このような幼少期をすごす中で、いつしか自分なりに没頭する対象を見つけてきて、知見を深めていくようになりました。
ディズニーで言えば、いま一番興味を持っているのは、アトラクションのメカニカルな仕組みや演出です(私はほぼ興味がありません)。
このように自分で世の中の様々なものに興味を持ち、世界を広げられるようになれば、半分は成功したも同然です。
逆に、「やりたい」より「やるべき」を優先させてきた場合は、この路線で行くのは困難なケースが多いでしょう。
なぜなら、いざ進学が迫ってきて、自分のやりたいことを考えなさいと言われても、十分な検討材料や選択肢を持っておらず、納得のいく道を選ぶことは難しいためです。
2.子どもの興味や得意分野にあったキャリア・進学先のアイデアをリストアップする
それまでにどのような経験をし、結果として何に興味を向けるようになるかは、家庭ごとに、あるいは当人の個性により、千差万別です。
「興味を持つ力」を重視して育てられてきた子であれば、誰しも、好きなもの、得意なこと、他人とは違う武器が何かしらあるはずです。
その子ならではの武器を活かして、社会で活躍するとしたら、どんな選択肢があるか? アイデアをリストアップします。
これは社会の先輩である親の出番が多くあります。
知らないものは「やりたい」とは思えません。子どもの限られた知識だけで考えさせるのではなく、人生経験や知見を活かして、「こんなのもあるよ、おもしろそうだね」と、たくさんのアイデアを出してあげましょう。
ただし、繰り返しますが、10代以降の子どもは、親の過干渉をストレスに感じ、中には強烈に反発する子もいます。
あくまでもアイデア、一つの提案にすぎない、というスタンスを崩さないようにしましょう。
長女に対しては、10個提案して1つ2つでも興味を持ってくれればいい、というくらいの気持ちでアプローチしてきました。決めるのは長女自身です。
具体的なキャリアについては、長女の場合は「謎解きイベントがつくりたい」という話があったので、リアル脱出ゲームを制作しているSCRAPへの就職を目指すのはどうか、というアイデアを出したところ、イメージの具体化へと動いていきました。
3. キャリアイメージを具体化できるような実体験・経験をさせる
10代前半で将来のキャリアイメージを具体化しようとしても、普通は困難です。なぜなら、社会や世の中を知る機会が限られるからです。
たとえば、「動物が好きだから獣医になりたい」というとき、子どもは獣医の仕事のなんたるかをまったく理解していないはずです。
現実には、動物の死に毎日のように直面し、思いの強い飼い主とのコミュニケーションに苦心する、心身の負担が大きい職業とされます。
幼い子どもが言う “憧れの職業” ではないので、知り合いの獣医がいれば話を聞いたり、職場見学をさせてもらったり、その仕事についての実感を持てる経験をさせてあげる、ということが非常に重要になってきます。
長女の場合は「人の心を動かすイベントをつくりたい」という目標であるわけですが、私が親子向けに様々なイベントを企画してきているため、イベントの企画・運営の裏側は、実は幼少期から見てきています。

子どもが主導するイベント企画で中心的に活動した経験もありますし、フリーダム・アイランドのパラダイスデー内でクイズ大会に出題者として参加することもしばしばありました。
もちろん、謎解きイベントやリアル脱出ゲームにも実際に参加して、作り手や運営側の動きを見るということもしています。
こうした経験があるため、自分と地続きの現実的な目標として考えることができています。
10代前半でキャリアイメージを具体化する詳しい方法論については、「総合型選抜「将来のキャリアイメージ」10代前半で具体化するために欠かせない5つの手順 – fly away」で詳しく解説していますので、合わせてご覧ください。
4. キャリアイメージから逆算して、最適な成長の場となり得る大学・学部を探す
たとえば、弁護士になるのであれば、法学部のある大学へ進学するケースが大半なわけですが、ひとくちに弁護士と言っても、ジャンルや分野、指向性は様々です。
民事で目の前の困っている人を助けたいのか、企業法務で影響力の大きい仕事がしたいのか。後者ならば法律の知識だけでなくビジネスの知識も必要です。
こうして考えていくと、社会に出る前に、どのような環境で知識やスキルを身につけ、成長する必要があるのかが、見えてきます。
基本的には、大学という環境が効率的な場合が多いでしょうが、専門学校に行ったほうがいい、あるいは学校に行かずに経験と実績を積み重ねていくのが最善という結論だってあるでしょう。
ここでは大学への進学に絞って話を進めていきますが、大学・学部選びも、親の出番が多くあります。
インターネット検索をするだけでも、意外と興味深い大学・学部が見つかります。
言うまでもありませんが、判断基準は大学名ではありません。将来のキャリアイメージから逆算して、最適な成長の場かどうかです。
合いそうな大学・学部が見つかったら、単に子どもに提案するだけでなく、なるべく早く、候補の大学に実際に足を運ぶ機会を作りましょう。
長女の場合は、「ディスカバ!」のワークショップがあり、桜美林大学の新宿キャンパスに足を運べたのが幸いでした。実はワークショップ参加は2回目で、中学2年生の夏休みにも参加しています。
中学生ですので、高校を飛ばしてになりますが、それでもキャンパスを実際に訪れて、そこにいる学生や教授陣に触れた経験は大きいです。あそこで学ぶんだ、と目の前の現実感のある目標に変えてしまいましょう。
5. 入試形態をリサーチし、実績づくりを始める。高校選びも実は重要
将来のキャリアイメージから逆算して、最適な成長の場となり得る大学・学部がある程度絞れてきたら、今度は入試形態についてリサーチを始めます。
大きく分けると、次の4つです。
- 一般選抜|テストの点での入試
- 学校推薦型選抜|指定校推薦|高校側が選抜。学校の内申(評定平均)や校内外の活動実績+αでの入試。
- 学校推薦型選抜|公募制推薦|大学側が選抜。選抜方法は総合型選抜に似る
- 総合型選抜|学校の内申(評定平均)は問われる場合が多い。選抜方法は、テストの場合もあれば、レポート・小論文、プレゼンテーション、グループワーク等の場合もあり、様々
それぞれの違いや、対策の考え方については、「総合型選抜、学校推薦型選抜|大学入試の特徴と対策の考え方 – fly away」で確認してください。
今回紹介した、桜美林大学の探究入試Spiralは総合型選抜です。「興味を持つ力」を最大限に活かすには、総合型選抜が最適な場合が多いでしょう。
しかし、分野によっては、総合型選抜の枠がほとんどないものもあります。

たとえば長女の場合、北海道の競走馬生産牧場で働く、という候補も実はあります。実際に生産牧場を訪問して話を伺ったところ、獣医の資格がある人材ならいつでもほしいという話でした。
この場合、真っ先に浮かぶ進学先は、国立大学の帯広畜産大学になりますが、一般選抜(テストの点での入試)が現実的になります。
いずれにしても、入試形態によって、準備すべきことがまったく変わってきます。
国公立大学を目指す場合には、当面は一般選抜が主流でしょうから、シンプルに学力を上げるために、中高一貫校や、進学実績の良い高校が有利になります。
一方で、総合型選抜のように、経験や実績を重視する選抜方法の場合は、進路にあった活動に力を入れている高校や、課外活動に専念できる高校を選んだほうが有利です。
つまり、高校受験も、「できるだけ勉強して、入れる中で偏差値が一番上の高校に入る」というものではなくなっています。
「興味を持つ力」を最大限に活かすキャリア形成・進学を目指すなら、高校選びは非常に重要です。
プレゼンは「聴衆を飽きさせない」が最優先!
フリーダム・アイランドの自由研究作成ワークショップは、ビジネスシーンでも通用する、レポート作成とプレゼンテーションのエッセンスを、楽しみながら学べてしまいます。

ボーダレスに世界と繋がる。「自由」の本質を学ぶ。自立のための一歩を踏み出す。10代前半(小学高学年〜中学生)が “興味を持つ力” を武器に進学/キャリア形成を目指すための、実践型探究学習プログラム。
